
 |
野村雅夫 フィルム探偵捜査手帳跳ね返る笑い ~ファミリー・ツリー~ |
|
 |
河原尚子 「茶」が在る景色光を想う |
|
 |
小林哲朗 モトクラ!ディスカバリー山のセメント工場 |
|
 |
ミホシ 空間と耽美壁と黒髪のカメレオン |

インタビュー 西村佳哲 さん
(聞き手・進行 牧尾晴喜)
デザイナーをはじめとする様々なひとへのインタビューを通じ、仕事の在り方を考える「働き方研究家」、西村佳哲さん。彼に、働き方研究に取り組むようになったきっかけやその姿勢、最近の著作についてうかがった。
------奈良県で2009年から2011年までの3年間、トークセッション・イベント『自分の仕事を考える3日間』でファシリテーターをされました。のべ3,000人の参加者、約30名のゲストとの場を重ねられ、各回が一冊の本としてそれぞれ出版もされています。まずは、このイベントについて教えてください。
西村: 奈良県立図書情報館が2005年に竣工して、開館記念企画で声をかけてもらったんです。担当の方が、仕事をテーマにして何か企画できないかと思っていたらしく、ぼくの著書『自分の仕事をつくる』で興味をもってコンタクトしてきてくれました。
最初の3年間、単発でゲストを迎える2~3時間のイベントをしました。ぼくは3回で一区切りということが多くて、このイベントもそこで終わろうとおもっていたけれど、館側には「もうちょっとやりませんか?」という雰囲気もあったんです。そこで、次はもう少し大きな3日間くらいのプログラムがいいなと考えました。ひとつには、オフシーズンの奈良に全国からひとが集まるようなイベントを作りたかったんです。もうひとつの理由は、ひとの話を聴くということを集中的におこなう時間をつくりたかったからです。
ひとの話を聴いたり本を読んでいたりして、何かに気づいたり、はっきりしなかったことがまとまりを得たりします。要するに、そのひとの話や文章を通じて、自分に出会いなおすわけです。本一冊を読むときは、だいたい何日かかけてその世界にいくわけですが、フォーラムやトークイベントだと2~3時間ということが多い。そうすると、次の日には普段の状態に戻ってしまうんですね。だから、3日くらいの長めのスパンで、「こういう風に働こう、生きよう」といったバイアスもなく、来たひとたちが自分で考えられる空間になってたら素敵だなあ、と。
------奈良での『自分の仕事を考える3日間』は3回で終了しましたが、続編などは?
西村: 続編ではないんですが、番外編みたいな感じで、『「自分の仕事」を考える2日間in札幌』を6月に開催します。奈良でのイベントは3年で終わる予定だったんですが、mina perhonen(ミナ ペルホネン)デザイナーの皆川明さんや建築家の中村好文さんたちがすごく仲良くなって、今度は札幌でやろうよ、ということになって。季節がいいときの北海道で、面白いメンバーでのイベントを体験してもらえます。
------「働き方」を研究してみようと思われたきっかけは?
西村: 大学を卒業してから鹿島建設の設計部で働いていたんです。通常業務とはべつに研究開発プロジェクトがあって、オフィスの研究をしていました。たとえば掲示板のレイアウトや形式が変わると、コミュニケーションの質がどう変わるか、といったことを研究していたんです。そういう研究をしていくなかで色々なことが分かってきて、そもそもひとにとって仕事の意味は何か、ということを真剣に考えるようになったんです。
------働き方を調べるため、おおくの方々にインタビューをされています。こういったインタビュー対象のひとたちについては、どうやって選んでおられますか。書籍では、「以前から気になっていた○○さんにインタビューした」といった表現もありますが、どういうところが気になったんでしょうか?
西村: 以前と最近では違うんですが、そのひとと自分の相性が合うかどうか、というのが大きいです。相性が悪いひとだとうまくインタビューもできないですし、あまり近づかないようにしています(笑)。依頼をうけて誰のところにでも行って機能するタイプの、プロのインタビュアーやライターではないんです。そういうトレーニングや自分へのプレッシャーは与えてないですね。
「気になっていた」というのがどういうことか考えてみると、「わからない」ということでしょうね。自分のなかで情報処理しきれない、しまえない、ということです。新しいひとに出会うと、たとえば「建築のひと」、「アウトドアのひと」、といった感じで「フォルダ分け」をしてると思うんですが、どこにもしまえないことがあります。映画でも、ホラーなんだけど恋愛小説みたいなところがある、だとか、うれしい曲だか切ないのか叫んでいるのか、全部が同時にせまってくるような音楽だとか。
そうやって「しまえない」のはずっと持ってるしかないんです。ひとを「持ってる」というのも変ですけれど、心に留めているというか、デスクトップに置きっぱなしというか。
そんなふうにして、気になったことをインタビューで確かめに行きます。でも、行ってみたところで、その相手のことが分かるわけではないです。「新しいフォルダができる」という感じですね(笑)。
------インタビューをする際に心がけておられることは?
西村: 先まわりをしない、ということですね。話を聴いていて、「あ、それってこういうことですよね」みたいなことはしません。そういうことをやっていくと、自分の理解の範疇だけの話になってしまい、自分が聞きたい話を喋ってください、という感じになってしまうんです。そのひとは一体どんなことを感じて、どんなふうに生きて、働いているのか、ということに立体的に触れていきたいので、そういうことはしません。
------新刊『なんのための仕事?』が出ますが、どのような位置づけの本でしょうか?
西村: むかし『自分の仕事をつくる』という本を書きました。デザイナーたちの仕事や働き方についての話を通じて、デザインやクリエイティブに限定されない仕事や働き方のことを考える、といった本でした。デザイナーやデザインに興味を持っているひとにしか分からないというような本ではなくて、わりといろいろなひとに読みやすくなっています。もともとぼくはデザイン畑の出身で、デザインという行為や営為を通じて、仕事や働き方のことを考え始めた人間なんです。だからそのテーマでさらに考えたことが『自分をいかして生きる』という本に続いたんですね。今度の『なんのための仕事?』で3部作になるという感じです。もし前の2作を読まれた方がいたら、ぜひ読んでほしいですね。
以前の『かかわり方のまなび方』という本で3部作かなあという気もしていたんですが、いま思えばあれは「外伝」ですね。働き方じゃなくてかかわり方、コミュニケーションの話になっているので。こちらは、働き方というテーマの横を流れていた、自分にとって大事な別の内容をあつかった本です。
そして『なんのための仕事?』では、デザインにフォーカスしています。というのは、ぼくはこの10数年間、デザイン教育にも携わってきましたが、みんな本当にデザイナーになりたいの?という疑問があったんです。忙しいよ、眠れないよとかいうことではなくて、自分が信じても愛してもいないことに情感的な魅力を与えるというようなことをやらされる可能性もあるけれど、それでいいの?と。これはデザイナーだけの問題ではないです。みんな仕事をしたいし、他人に認められたり必要とされたり、あるいは存在を確認できたり、社会での居場所を得たりと、仕事は強力なメディアでもあります。ただ、それと引き換えに何をやらされているのか、という感覚があって。そこを確かめ、言語化したかったんです。
------最近の著書のひとつ『いま、地方で生きるということ』では、執筆にあたって、震災の影響も大きかったとおもいますが?
西村: 震災がなかったら、まずこの本は出てなかったでしょうね。あの本は、自分で書いたという感じではないんです。出版社の三島さんに書かされたという感じです(笑)。もちろん、被害者意識なんかではなくて、喜んで書かされたという意味ですけれど。
三島さんとは奈良のフォーラムで出会ったんです。このひといいなあと話を聴いていて、本のオファーはうれしかったんですが、テーマが「地方」だったので難しすぎるなあ、と。単に地方を語るのではなく、この国、近代をどうとらえるか、という話なので。
これからは地方の時代だとかいう言葉がよく聞こえていたけれど、ぼく自身、まったくピンときていなかった。「都市対地方」みたいな二項対立の図式自体に抵抗感があったんです。「これからは地方の時代」といったフレーズを聞くと、その「時代」もいつか終わるんですか、その時代は何年つづくんですか、というふうに思っていました。ただ、どういう問題があるだとか、それをどう言語化するだとか、以前は頭のなかにまとまっていなかったんです。三島さんが産婆さんみたいになって、一緒に出した、という感じです。
------長谷川浩己さんと山崎亮さんが様々な分野のひとたちとデザインについて語る『つくること、つくらないこと: 町を面白くする11人の会話』にもゲストで登場しておられます。
西村: 長谷川さん、山崎さんとはそれまで面識はなかったんですが、ぼくの本『自分の仕事をつくる』を読んでくれてたみたいで、ゲストで話をさせてもらいました。
------西村さんは仕事の背景としての価値観、さらには自身のあり方などにも触れておられるのがとくに印象深いですね。長谷川さんたちもおっしゃっていましたが、途中から立場が逆転して、西村さんが聞き役にもなっていました(笑)。
つぎに、リビングワールドでのデザインのお仕事についてうかがいます。太陽の光が地球に届く時間を示す砂時計、などもデザインしておられます。モノづくりのテーマは「センスウェア」とのことですが、どういったものでしょうか。
西村: 「センスウェア」を言葉で表現すれば、世界を感じる道具の総称です。たとえば風鈴。あれは、べつに楽器ではないですよね。海外のウィンドチャイムは複数音階で、ある和音が生成・再生されるものがおおいですが、日本の風鈴は単音で、チーンとしか鳴らない。あれは何をしているんでしょう?日本の風鈴は軒先に吊るしてあってただ「風が吹いています」ということを伝えている。あれは、風が吹いているということに対する意識や人間の感覚を拡張する装置になっているとおもうんです。心もそうだし、身体もすこし開く。風が吹いていることに対して敏感さを増す。
凧を300メートルくらい上空まで飛ばしているとして、そのとき、凧の先っぽまで自分の一部ですよね。ぼくたちの感覚は結構のびます。自転車でタイヤがかんでいる石の感覚もわかるし、箸をつかっているときは箸の先まで自分だし、そうやって意識すると運転や食事の仕方も変わります。「どこまでが自分か」は割と伸び縮みしているんです。メンタルな意味合いでも感覚的な意味合いでも、その伸び縮みを取り扱う道具がセンスウェアです。自分がどんな世界のなかで生きているかを感じとったり、認識できた瞬間、ひとは嬉しそうになるというか、そこに面白さがあると思います。これまでそういったことを意識せずに生きてご飯を食べて呼吸をして話をして、というひとが、こんなところで生きているんだ、と再確認できるような時間や空間をたくさんつくりたいという感覚が以前からあったんです。さっきの「太陽の光の砂時計」はそれを砂時計というパッケージでやったシリーズですし、その前には風鈴の代わりに風で灯る光、『風灯』などもつくっています。中之島の関電ビルディングの頂部につくった、日没とともに灯って風の動きを映すインタラクティブな照明システム『リブリット』なんかもそういう例ですね。
------どんな子どもでしたか。
西村: 子どものころのぼくは、近所の子どもたちで「ごっこ遊び」をするときに、その日にどんな遊びをするか、シナリオや場面設定をして配役をする、といった感じでした。プランナーなんですね。アイデアを出して、いっしょにやって、そのなかで自分の役割はこれ、と。何かをおもいついて形にする、それで皆に声をかけるのが好きなんです。好きというよりも、ぼくのなかで、パソコンのOSのように作動する感じですね。いまも、自分が起点になっている仕事では、たとえばイベントとかもワークショップの企画も、まったく同じOSで動いています。何かをおもいついて、必要なひとたちに集まってもらって、自分も一緒になって運営して、形にして解散する、ということを繰り返しているんです。
小学校で複数の人間のあつまりのなかでどんな風に動いていたか、というのは大人になってもそんなに変わらないんじゃないかな、という気がしている。むかし鹿島建設でランドスケープデザインのひとたちと仕事をしていたときも、このひとたちは砂場でこんな遊びをしてたんじゃないかなあ、と想像したりしてました(笑)。
------子どもの頃のことも、建築分野でのお仕事も、すべては、いまのお仕事につながっていますね。
西村: 振り返ればすべてつながっています。ただ、事前にはつながらない、というか分からないですよね。そのときどきは夢中になってやるだけで、夢中になればその結果は塊になるし、それが点になってあとでつながります。起点になる。
------関西で好きな場所はありますか?
西村: 総じては言えないかもしれないけれど、大阪のひとたちは、東京とは距離感が違います。打合せでどこかの事務所に行ってて、別のスタッフが通りかかったとして、東京だったら「西村さん来てたんですね」「お邪魔してます」みたいな立ち話で、去りますよね。それが大阪だと、「西村さん、何してはるんですか」とか言いながら、横に座ることがある。「え、座るの?」みたいな(笑)。この距離感や近づき方、関わり方がおもしろいです。東京者としては居心地がいい。そういう人なつっこさが大阪の居心地なのかもしれません。ですから、場所というより、大阪に来て誰かにあうのが好きですね。
------5月にもイベントで大阪に来られますから、楽しみですね。
西村: 5月28日に、心斎橋のスタンダードブックストアでトークイベントがあります。『なんのための仕事?』の刊行記念イベントで、大阪のデザイナー、原田祐馬さんと話をしようということになっているんです。楽しみですね。
------今後のビジョンを教えてください。
西村: この2、3年くらい、本を書いてばかりだった感じがあります。そういう状況には、こんどの『なんのための仕事?』で、一区切りになります。そうやって本を書いているあいだ、時間を取れずにきたのが自分の会社、リビングワールドのことです。そっちをこれからどうするかにエネルギーを注いでいきます。
2012年3月22日 大阪にて
 |
|
わたしのはたらき 自分の仕事を考える3日間III (著)西村佳哲、弘文堂、2011年11月 |
 |
|
「自分の仕事」を考える2日間 in札幌
|
 |
|
いま、地方で生きるということ (著)西村佳哲、ミシマ社、2011年8月 |
 |
|
つくること、つくらないこと:町を面白くする11人の会話 (編)長谷川浩己、山崎亮、(著)太田浩史、廣瀬俊介、鷲田清一、ナガオカケンメイ、鈴木毅、馬場正尊、西村佳哲、芹沢高志、広井良典、学芸出版社、2012年2月 |
 |
|
自分の仕事をつくる(ちくま文庫) (著)西村佳哲、筑摩書房、2009年2月 |
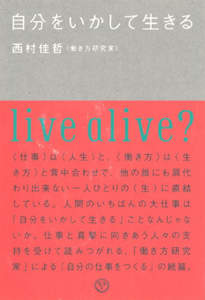 |
|
自分をいかして生きる(ちくま文庫) (著)西村佳哲、筑摩書房、2011年6月 |
 |
|
砂時計:太陽の光、月の光 In this time "ある時間"をしめす砂時計のシリーズより |
 |
|
Photo:後藤武浩(ゆかい) 西村 佳哲(にしむら よしあき) 1964年東京生まれ。働き方研究家。コミュニケーション・デザインの会社リビングワールド代表。 武蔵野美術大学卒業後、建築設計分野を経て、つくること・書くこと・教えることなど、大きく3種類の仕事に携わる。 著書に、『自分の仕事をつくる』(晶文社/ちくま文庫)、『わたしのはたらき 自分の仕事を考える3日間III』(弘文堂)、『いま、地方で生きるということ』(ミシマ社)、など。 |

跳ね返る笑い ~ファミリー・ツリー~
やあ、私だ。かつて留学していた頃、友人から「毎日がローマの休日なんて羨ましい」だの言われ、「てやんでい! こちとらローマの平日なんだ」と返していたものだから、ジョージ・クルーニー演じる主人公の気持ちはよくわかる。「ハワイに暮らしていても、人生は楽じゃない」
カメハメハ大王の血を引き継ぐ弁護士マットは、代々受け継いだ広大な土地を売却して一族に巨万の富をもたらすのか、自然環境を優先させるのか、自分のルーツと家族・親族の懐を同時に勘案しなければならない状況にいた。そこへ不意に妻が海の事故で昏睡・植物状態に陥ったうえ、反抗期真っ盛りの高校生の娘からは妻が不倫をしていて離婚まで考えていたと知らされる。10歳の娘もショックから精神的に不安定になってしまい…。
深刻極まりない、下手をすれば目も当てられないこの設定に、ペイン監督はユーモラスな視点を導入することで、『アバウト・シュミット』や『サイドウェイ』で見せたスタイルを研ぎ澄ませている。
曇りがちな空。枯れ葉の浮かぶ自宅のプール。シルバーの日本製セダン。景色、居住空間、移動手段、どれを取っても「冴えてる」とはお世辞にも言えない「楽園」の断片に囲まれながら、マットは爆発寸前の感情と弁護士的な理性や調整能力の板挟みになる。文字通り画面を右往左往するごとに、哀れな中年男のしょぼくれ具合がずるずると否応なしに露見する。
この作品にははっきり間違った人もはっきり正しい人も出てこない。逆に言えば、誰もが正しくもなく間違ってもいない。私たちがスクリーンを前に顔を引きつらせながら笑ってしまうのはそのせいだろう。誰かのどこかに自分のトホホな要素と共通する点を見つけてしまうのだ。
ラストシーン。ソファに並んで座り、デザートを順繰りに回し、毛布を分かち合いながら見るともなくテレビを見る父と娘ふたり。苦難を乗り越えた愛すべき家族の風景と見るか、やはり冴えないプチブルの空虚さと捉えるか。その解釈でマットよろしく揺れ動く自分に気づき、私の頬はまたピクリと動いた。
 |
|
(c)2011 Twentieth Century Fox ファミリー・ツリー 公開日 2012年5月18日(金) 公開劇場 TOHOシネマズ 日劇他 全国ロードショー スタッフ 監督:アレクサンダー・ペイン、脚本:アレクサンダー・ペイン、ナット・ファクソン、ジム・ラッシュ キャスト ジョージ・クルーニー、シャイリーン・ウッドリー、ボー・ブリッジス、ジュディ・グリア、アマラ・ミラー |
 |
野村雅夫(のむら・まさお) ラジオDJ。翻訳家 FM802でROCK KIDS 802(毎週月曜日21-24時)を担当。知的好奇心の輪を広げる企画集団「大阪ドーナッツクラブ」代表を務め、小説や映画字幕の翻訳も手がける。 |

光を想う

四月に入って一週間も経つと
まるでスイッチを切り替えたように、光がかわった。
灰青の空に桜が舞う。
これが 真っ青な夏空だったら
桜の色は白と言われていたかもしれない。
かすかにピンク色をした桜を、まだ淡い光がなぞらえる
「光」というと
昔 旅行でスペインに行った時の、あの真上から降る光を思いだす。
どこまでも透き通った青い空に、黄色い壁の家。
原色で描かれたタイルに光がきらきらと当たって
赤や黄色や緑の原色が、街の風景に溶けた。
茶の湯でも光の移ろいはとても重要に演出される。
茶事の途中、簾を長いものから短いものに付けかえる。
仄暗い部屋に光がはいり空気が一新する。
陰から陽へ そこに時間の概念がプラスされ厚みが生まれる。
文化は太陽から創られる と思った。
もしかしたら 人も光から創られるのかもしれない。

 |
河原尚子(かわはら・しょうこ) 陶磁器デザイナー/陶板画作家 京都にて窯元「真葛焼」に生まれる。 佐賀有田での修行を経て陶板画家として活動を開始。 2009年、Springshow Co.,Ltdを設立。同年、陶磁器ブランド「sione」を発表。 |
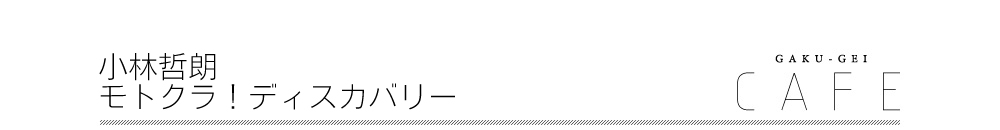
山のセメント工場
 |
とある地方の高速道路を走っていると、不意に目に入って来た巨大な設備。気になったので次のインターを降り早速向かった。特徴的なプラントから、すぐにセメント工場だとわかった。視界を埋め尽くすほど臨海部に広がる工場群は圧巻だが、素朴な山をバックにしつつ、メカメカしさをむき出しにした長身のプラントも十分に異世界を感じさせてくれる。
 |
小林哲朗(こばやし・てつろう) 写真家 廃墟、工場、地下、巨大建造物など身近に潜む異空間を主に撮影。廃墟ディスカバリー |

壁と黒髪のカメレオン
 |
黒髪のカメレオンが居る。
壁に添うように俯き加減にあやとりをしていた。
夢中になっているのか、体が時々揺れる度に木目のようなワンピースから白い四肢が見える。
どきりとした。
これも男の目を惑わす一種の擬態なのだろうか。
何食わぬ楚々とした顔で獲物を待っているカメレオンのように思えてならない。
心と体の隙をつき、糸を手繰り寄せて密林という名の壁に捕獲する。なんて…。
春のせいか私の頭の中が少しぼうっとしているようで、のっぺりとした壁も呼吸しているようにみえる。
まるで生物のようだ。そしてそこには、擬態する少女。
変わらず黒髪のカメレオンはあやとりに夢中だ。
このままそっと、カメレオンに近づいたらどうなるだろう。
食われるだろうか、それとも…。
 |
ミホシ イラストレーター 岡山県生まれ、京都市在住。イラストレーターとして京都を拠点に活動中。 抒情的なイラストを中心に、紙媒体・モバイルコンテンツなどのイラスト制作に携わる。 |


 |
第1回
講談師 |
 |
第2回
フォトグラファー |
 |
第3回
同時通訳者 |
 |
第4回
働き方研究家 |
 |
第5回
編集者 |
 |
第6回
日常編集家 |
 |
第7回
建築家ユニット |
 |
第8回
劇作家/小説家 |
 |
第9回
アーティスト |
 |
第10回
プロデューサー |
 |
第11回
インテリアデザイナー |
 |
第12回
ライティングデザイナー |



























