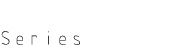
 |
野村雅夫 フィルム探偵の捜査手帳ぽつねんとあるポット ~再生の朝に -ある裁判官の選択~ |
 |
澤村斉美 12の季節のための短歌すずかけのきの下を行くときすでに鳴り出しているわれの音楽 |
 |
小林哲朗 モトクラ!ディスカバリー東大阪ジャンクション |

インタビュー 小川勝章 氏
(聞き手・進行 牧尾晴喜)
江戸時代からつづく屋号のもとで庭づくりに取り組む作庭家、小川勝章氏。彼に、庭に対峙する姿勢や、現代都市における人と自然の関係についてうかがった。
------まずは「作庭家」のお仕事についてうかがいます。「庭をつくる」ということについてお聞かせください。
小川: だいそれた表現になってしまいますが、お庭づくりというのは、地球そのものに触るお仕事です。泥だらけになりながら、地球に触ってお庭をつくらせていただくという、尊くて責任がある仕事だとおもいます。目の前で地球の一部を再構築できるんです。
たとえばお庭に山をつくることを「築山(つきやま)」と呼びますが、そのために土を運んできたり、樹や石を山や川からもってきたりします。昔は牛がひっぱってきていたのが、いまはダンプカーで運ぶ、といった違いはありますが、いずれにせよ、こういったものはすべて、地球のどこかから持ってくることになります。そしてそれがどんなに大きな作業であっても、地球規模でみればすごく些細なことで、ちょっと移動したにすぎないんですよね。けれども、その場所は確実に変わっていきます。
------敷地のなかで建物と庭の両方が存在することが多いとおもいます。両者の関係性についてはいかがでしょうか。
小川: 「家庭」という言葉がありますが、そのように家、建物と向かいあうお庭が基本だと考えています。建築でも同じだとおもいますが、お庭づくりでも、そこで生活する人のことをまず考えます。人数や、どんな生活をするのか、どの部屋や場所で過ごす時間が長いだろうか、外部からのお客さんはどんなふうに訪ねてくるだろう、住んでおられる方はどんな音楽が好きだろう、などといったことです。そういったこととあわせて、どこからお庭をご覧いただこうか、何時くらいに見られることが多いだろう、と考えます。建物があって人がおられることが前提になることが多いですね。
お庭にもカオがあるんです。一般的に、一番よくお庭をみていただける場所に向かって、お庭の正面のカオを見せるようにします。もちろん、そのような正面のカオが基本ですが、人間の顔と同じで横顔がよかったりもします。向ける方向は住まい方によって変わるんです。
------『植治』の屋号は江戸時代から続いています。本質は同じでも、時代によって変わる部分もあるかと思うのですが、いかがでしょうか。
小川: そうですね、変わっているものは確かにあります。お庭の背景となる街自体が違いますし、それぞれのお庭の用途や大きさ、また、人の気持ちや考え方も変わっていきます。また、使える材料なんかも変わっていきます。たとえば、昔この辺りでは貴船石や鞍馬石、加茂川真黒石などといった良質の石をつかっていました。ちょっと手をのばせばなんとか届く、あるいは土地にゆかりがある、といったものを使っていたんです。いまでいう「地産地消」ですね。いまは遠くに手が届くようになり、逆に近くのものは持ってこれないこともしばしばです。
お庭づくりの本質としては、必ず樹がなければ、石がなければ、ということはなく、地球を感じることができるかどうかだとおもいます。風や雨や水や月、といった自然本来の姿を心地よく感じるということを、現代では忘れがちです。人間のこと、そして手つかずの自然を思い出せるような拠り所、接点となるようなお庭づくりを心がけていますが、こういう部分は昔から変わっていないとおもいます。
------小川さんは、歴代・当代が手がけられた庭の修景・維持をされています。これは、まっさらな土地に庭をつくるのとは違った難しさがあるかと思いますが、いかがですか?
小川: そうですね。目に見えているものは大事ですが、それが一番ではないんです。そこには、見えない、重ねられた思いがあります。モミジの色づきだけでなく、そのモミジの過去の思い出や、来年のモミジへの期待もあるでしょう。そういうふうに、昔のお施主様や歴代の先祖が庭に対して何を考えておられたか、察することがあります。本来はあの辺からご覧になっていたのだろうか、というふうに昔の日本家屋のことを紐解いていけたり、先人の思いを感じることができたりする幸せがあります。
------そういう修景・維持のお仕事でも、時間経過とともに庭は変わっていくんでしょうか?
小川: そうですね、自然のものですから、ずっと同じということはありえないです。でも、お庭の全盛期の状態へ復元しようとする折、本来であれば100歳の庭を、60歳に戻して、不老不死のように来年も再来年も60歳になるようにする場合があります。こういう経緯のときには、あぶないことがありますね。わたしたちがまったく同じ笑顔はつくれないように、笑っているような石の表情ひとつにしてもまったく同じ状態には復元できません。クレーンで石をすえ変えた時点で、微妙に異なってしまいます。
人間の人生と同じで、お庭にも浮き沈みがあって過去から未来へつながっていきます。見た目だけ整えて過去を消したり、とりつくろってみたりしても、ピカピカだけれど痛々しいお庭になってしまいます。ですから、人と同じでどうやってよい年を重ねていくか、というのが修景・維持のお仕事で大事だとおもいます。
------バーカウンターのある庭など、洋風のものもつくられていますね。
小川: そうですね、洋風のものもありますが、考え方のルーツは日本に根ざしたものだとおもいます。テイストは異なって見えるかもしれませんが、喜んでもらうためのポイントや見せ方は同じですね。
------どんな子ども時代を過ごされましたか?
小川: 両親がうまく誘導してくれたのか、「絶対に庭づくりをしなければ」という義務感はなかったですね。ただ、自分のなかでなんとなく意識はありました。小学校の頃の将来の夢では、その頃に流行っていた「警察官」、食べることが好きだったので「ケーキ屋」、そして「お庭づくり」、と3つも書いていました。欲張りだったんです(笑)。
小さなころに遊んでいたお庭のディテールは覚えていなくても、やさしい原風景となっています。サワガニを見つけたり、ウナギにびっくりしたり、こおろぎや赤とんぼを捕まえていました。そうやって包み込んでくれたお庭のイメージがありますから、やはり、子どものころに遊ばせてもらったのはありがたいですね。
年配のお施主様が、「昔は滑り台のようにしてこの石のまわりで遊んでいたんだ」というふうに教えてくださったことがありますが、そういう場面があるとよいですね。バーベキューでもなんでもよいですが、庭でのできごとがあれば、それがお庭との接し方や思い出につながっていくとおもいます。
------高校入学と同時に作庭の修行に本格的に取りかかるわけですが、修行は、どんなことから始められましたか?
小川: 最初は、スタッフの方々と一緒にひたすら掃除ですね。掃除、草ひき、水まきから始めます。こういった掃除というのは誰でもできそうだと考えますが、それだけに、プロとして掃除するのは大変難しいことです。毎日掃除にいくお宅もあれば、1年に1日しか行かない家もある。そうすると、残りの364日はお住まい方が掃除しているかもしれないわけですが、そういう方々に「さすが」と思ってもらえる掃除をしなければいけません。もちろん、毎日掃除させていただくお宅でも、漫然と繰り返すのではなく、その日毎に掃除で提供できる喜びとは何かを考えないといけません。ですから、たとえ少しのバイト料をいただくだけでも、最初は怖かったですね。
雑草をひくということについても、一般に雑草と思われている草の開花をお施主さんが楽しみにしておられるかもしれないし、気に入ったものを山から持って帰ってきたのかもしれません。雑なものは何一つありません。周りのお施主さんの気持ちも考える必要があります。誰でもできることほど難しいものはないですね。
------京都の街について。
小川: 皆さんが言われるように、歴史があります。いいことも悪いこともふくめて重なっている、ミルフィーユの状態です。昔から残っているものや思いの積み重ねがあって魅力的な街だとおもいます。そして、京都という街を背景にしたり力を借りることができますが、うわべだけで力を借りてしまうと、うまくいきません。京都の街に積み重ねられた見えない歴史や思いに敬意を払ってこそ、人もお庭もいきいきとしてきます。
------京都で好きな場所は?
小川: 特定の場所というのはないですね。よく「お勧めのお庭」を尋ねられるのですが、そういうときにも困ります(笑)。お庭づくりは自然にあこがれてのことですから、そのときその一瞬に出会うことができる自然が嬉しいです。たとえば、『無鄰菴』であれば、晴れている日にはお庭の奥、滝口から振り返ります。「水鏡」といいますが、まさに鏡のように空やモミジが水に映りこみ、その枝ぶりがフレームとなります。そこには、空が水と一緒に自身の心もひろがっていくような感覚があります。無鄰菴ではそんなところが好きですね。
------庭づくりというと和風の印象がありますが、一方で、海外の方々にとって興味深い対象でもあるとおもいます。
小川: 海外の方にお庭をご覧いただく機会もありますが、質問が、より突っ込んだものになることがあります。なぜこの木をここに植えたのか、自分の国と違う植え方になっているのはなぜか、など、背景にある考え方自体を問われることがありますね。
また、数年前に、ドイツ人のスタッフがいたことがあります。最初は日本語を話せませんでしたが、小さな辞書を持ち歩いていて少しずつ話せるようになり、日常会話には不自由しなくなりました。そのスタッフは、やがて今の日本人が忘れがちな微妙な日本的ニュアンスにも気づき始めました。つまり、人の心持ちも大事にする、言葉にならない言葉がある、行間を読む、といったことです。そういうふうに相手の思いを汲み取ろうとする努力をみていると、国籍だけを問題としているわけではないですが、海外の方に日本のことを感じさせられたこともあります。
------今後どのような庭づくりをしていきたいですか。
小川: 生活に根ざした、日常のお庭をつくりたいですね。いまは、非日常のものとしてしかお庭が成立しづらくなってきているとおもいます。どこかに行って入場料を払ってお庭をみるのだけれど、自分の家の前にある街路樹の種類もわからない、といった矛盾が起こっています。桜のような木についても、花が咲いている時期しか気にしないのですが、実際には咲いていない時期のほうが圧倒的に長いわけです。いろいろな時期があるのは人と同じなので、そのように色々な時期の桜の魅力にもお気付きいただければとおもいます。
お庭の大きさや雰囲気等は、責任を持てる範囲での向きあい方でいいとおもうのです。お手入れが大変で重荷になってしまう方もおられますが、あまりの無理は長続きしません。苦楽を共にする家族のように付き合える庭であればとおもいます。
日常のなかに、ほんの少しでも地球との接点があればいいなあ、と。
2011年4月28日 京都にて
 |
| サワガニの川 幼少期に戯れたあるお庭の川筋。サワガニとの出会いがお庭づくりの原点となる。 |
 |
| 枯山水と露地 近年に手掛けたある茶席の内露地。築山を大陸に、白砂を大海に見立てる枯山水の発想が、露地に重なる。(撮影:池田和) |
 |
| 蹲踞とシャンパンクーラー 近年に手掛けたあるショットバーの蹲踞。手を清める本来の用途に加え、シャンパンを清め尊ぶものとした。(撮影:池田和) |
 |
| おばあちゃんのすべり台 かつておばあちゃんが遊んだ大きな石。今その石の上には3世代が集い、語らいの場となる。 |
 |
小川勝章(おがわ かつあき) 作庭家。1973年生まれ。江戸時代より続く「植治」(うえじ)の屋号を継ぐ11代小川治兵衛の長男。高校入学と同時に11代のもとで修業を始め、現在は歴代・当代の作庭、修景などをおこなうとともに、オリジナルの庭も数多くてがける。 |

ぽつねんとあるポット ~再生の朝に -ある裁判官の選択~
法の下の人は、ボウルの中の豆腐ではないかと思うことがある。落としても豆腐だけ崩れてボウルは何ともないように、人ではなく法だけが守られることがままあるからだ。法を適用するのは人だが、判例・キャリア・面子といった事情は、その人から情を奪い去る。しかし、裁判官とて人の子だ。その葛藤がドラマを生む。
舞台は1997年、中国河北省の小さな町。盗難車によるひき逃げで娘を亡くしたベテラン裁判官が失意のうちに暮らしている。犯人は未だ見つからず、過去の判決がらみの逆恨みではとの噂が流れる。そこへ車2台を盗んだかどで、貧しい青年が連行されてくる。時は刑法改正直前。現行法にのっとり、驚くことに青年は死刑判決を受ける。二審でも覆らず、執行の日は迫る。ふいに、重い腎臓病を患う実業家が弁護士を介して現れ、執行後の青年の臓器を文字通り自分のものにしようと画策する…。この三方よしといくはずもない設定には唸らざるをえない。
裁判ものは時に字幕を追えないほどセリフが多くなるが、これはむしろ情報がギリギリまで削ぎ落とされている。カメラもほとんど動かない。画面は逆光気味でほの暗い。しかし、絵画的な完成された構図の中で蠢く人間の、か弱い心の移ろいを示唆する行動ひとつひとつを、私たちはかえって注視することになる。中国の人権意識の低い実話に触発されてはいるものの、監督に用があるのは、法ではなく人であることがひしひしと伝わってくる演出だ。
その証左として、私がひとつ挙げるとするとすれば、ポットになる。裁判官の自宅のつましいダイニングテーブルや、これまた色に乏しい裁判所内の詰め所に、そのさめざめとした雰囲気の中に、ぽつねんとあるポット。そこにあるだろう湯がホッとさせる。血の通った温もりや生活を想起させるのだろう。こうしたきめ細かな作りが、作品を「法廷もの」ではなく、人間ドラマにしているに違いない。
蛇足だが、私はフィルム探偵。捜査と評価はすれど、映画を裁くことはしない。
 |
|
(c) 2009 3C FILMS CO., LTD All Rights Reserved アルシネテラン配給 5月7日より 大阪・第七藝術劇場 5月10日より 神戸・元町映画館 近日公開 京都シネマ |
 |
野村雅夫(のむら・まさお) ラジオDJ。翻訳家 FM802でNIGHT RAMBLER MONDAY(毎週月曜日25-28時)を担当。イタリア文化紹介をメーンにした企画集団「大阪ドーナッツクラブ」代表を務め、小説や映画字幕の翻訳も手がける。 |

すずかけのきの下を行くときすでに鳴り出しているわれの音楽
光がつよくなってきた。プラタナスの木に青い葉がいきいきと育っている。プラタナスはスズカケノキともいい、街路樹として植えられていることが多い。樹皮がまだらで特徴的なので分かりやすい。
2000年に亡くなった歌人、永井陽子さんに名歌がある。
べくべからべくべかりべしべきべけれすずかけ並木来る鼓笛隊
古文単語「べし」の活用を暗記するとき、こんなふうに唱えたっけなあ。永井さんの歌は呪文のような「べし」活用を鼓笛隊の音にあてている。
新緑の眩しい季節、すずかけ並木を行けば、カエデに似た広い葉っぱがてんでに揺れて、おおざっぱに光をこぼす。リズミカルな光と影の動きを踏みながら、いかにも小太鼓が似合う木だ、と思うのだ。
 |
澤村斉美(さわむら・まさみ) 歌人。 1979年生まれ。京都を拠点に短歌を見つめる。「塔」短歌会所属。 2006年第52回角川短歌賞受賞。08年第1歌集『夏鴉』上梓。 |
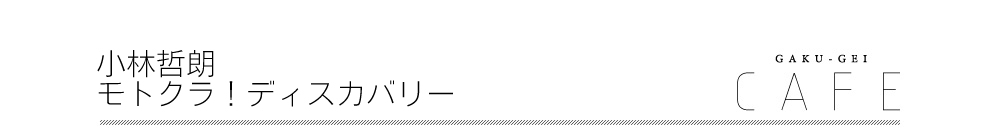
東大阪ジャンクション
 |
大阪府東大阪市役所の22階展望ロビーからは、普段あまり見ることのできないジャンクションの全容を俯瞰で眺める事ができる。見られるのは阪神高速と近畿自動車道をつなぐ、「東大阪ジャンクション」。玩具のような大きさの車が、それぞれの目的に向かって分岐していく様子は見ていて飽きない。日が沈むと高速道路はヘッドライトの河になり、日中とはまったく違う雰囲気を楽しめる。ゆったりと見物するのがオススメだ。
 |
小林哲朗(こばやし・てつろう) 写真家。保育士 保育士をしながら写真家としても活動。廃墟、工場、地下、巨大建造物など身近に潜む異空間を主に撮影。廃墟ディスカバリー |




























