
 |
橋本征子 建検ガクガク#3 コンテナの可能性 |
 |
野村雅夫 フィルム探偵捜査手帳雨のち星、やがて恋 ~マジック・イン・ムーンライト?~ |
 |
寒竹泉美の月めくり本2015弥生本「日本酒ガールの関西ほろ酔い蔵さんぽ」 松浦すみれ (著) |

インタビュー 山岸剛 さん
(聞き手/牧尾晴喜、原稿構成/風戸紗帆)
写真を通して、建築、さらにはその先に見えてくる自然を伝える山岸剛さん。東北での撮影やヴェネチア・ビエンナーレなど国内外で注目を集めるプロジェクトに携わる彼に、「建築写真」の魅力をうかがった。
-------まずは、昨年末に刊行された大型本『井上剛宏作庭集 景をつくる 』についてお聞かせください。
山岸:東北から九州まで全国で作庭をされている井上剛宏さんの仕事を1年半かけて撮り下ろしました。井上さんは京都で二百年続く植芳造園の当主です。庭師ですね。風景そのものをつくりだすかのような九州や東北でのスケールの大きい仕事と、京都でのいかにもつくり込んだ小さな庭は、一見まったくちがう仕事のように見えますが、彼のものの見方はつねに一貫しています。ですから僕もそれに沿うように、彼の考え方をなぞるようにして撮影しました。
従来のいわゆる「庭の写真」は、いわば建築写真のように撮られることが多かったのですが、この本ではごくふつうの風景を撮るように、庭を歩いていく経験をそのまま写真にするような感覚で撮影しました。つまり、庭を歩いて、何かが目について近づいてみて、さらにまたその先へ歩を進める、というような行ったり来たり、近づいたり離れたり、という経験の連続と不連続を写真にするということですね。その点ではこれまでの庭の写真とは違うものになっていると思います。
-------「建築写真のように」という言葉がありました。一般的に、建築物が竣工したときに記録や宣伝などの目的で商業的に建築写真を撮影することがありますが、山岸さんの考える「建築写真」とは?
山岸:いわゆる建築写真というのは、建築家の設計意図をきちんと美しく撮る写真ですよね。むしろ建築家の意図のみを、と言えるでしょうか。たとえば住宅建築で、若い夫婦が希望に満ちてあたらしく住みはじめる家と、老夫婦のための終の棲家とでは家がもつイメージがまったく異なるはずですが、一般的な建築写真ではそういった要素は考慮しません。そういう建築写真は必要なものです。でも、それだけである必要はぜんぜんない。
建築って、膨大なものが流れ込んではじめてカタチになって建ちあがるものです。まさに人工性の結晶です。人類の歴史とともにある、本当に豊かで、力強いものだと思います。設計した建築家の意図を尊重するっていうのはとても大事なことですが、それは建築を建ちあげる条件のうちのひとつでしかありません。ある建築が町にあたらしくできて、向こう三軒両隣とどういう関係にあって、そのことで町の風景がどんなふうにちがって見えてくるのかとか、建築って風景まで変えてしまうすごいものだと思います。そういう建築の豊かさとかみずみずしさを感じることができる写真をぼくはつくりたいです。たんに設計図面通りに撮るのではなくて、自分がそこに立ったときの感覚を、写真を観る人にもそのまま伝えられるような写真にしたいと思っています。
-------たとえば、西沢立衛さんが設計された「森山邸」を撮影されていますが、その際はどのような感覚がありましたか?
山岸:いまそこいらで新しく建つ家って一言で言えば、安心安全快適って感じですよね。さらにいろいろ高性能なんでしょうけど、なんか閉じてて風通しが悪そう。森山邸というのはその対極です。窓もやたらデカいし壁も薄いわで、敷地は隙間だらけなんで近所のおばちゃんやら子供やら猫やらが平気で入ってきてなんか動物園みたい(笑)。ここでは、人間もふくめたある種の自然をダイレクトに感じることができます。まさにダイレクト、直接的、すぐ近くという感じ。寒いときは寒い、暑いときは暑いよ、みたいな。ワイルドですね。でもちがう意味で快適なんです、ほとんど至福です。ご主人の森山さんはほとんど家から出ませんからね、いつもご満悦状態なんでしょう(笑)。森山邸の素晴らしさについて、設計に関しては門外漢で分かりませんが、あの建築は東京のあたらしい自然を発明したとぼくは考えています。あの建築があそこに建つことではじめて東京の自然が見えてきた。「東京の自然」、というのはとても見えにくいですよ。東京は人工性に埋め尽くされていますから。
-------東日本大震災以降、東北での撮影を継続されています。経緯や問題意識についてお聞かせください。
山岸:もともと、妻の母方の実家が盛岡にあるという縁があって東北に毎年行くようになって、まあ写真家なので盛岡周辺で撮影もしていました。2010年の8月にはじめて沿岸部にも足をのばして撮影をはじめたら翌年、あの地震、津波、原発事故が起きた。以前は、災害とか事件事故が起きた現場に写真家が群がるのは恥ずかしいことだと思っていましたが、このときにはすぐに写真家としての自分の仕事だと感じました。これは東京の問題だと思ったし、それを自分なら撮れると思いました。
さっき森山邸の件でお話した、建築という人工性をとおして自然が見えてくる、自然を見つめることで今度は人工性が浮かび上がる、そういうものの見方で、ふだんの撮影と同じように東北を撮っています。ぼくにとっては建築の写真も東北の写真も同じです。結果的に被災地を記録することになりますが、被災地だけを撮っているわけではないし、ジャーナリステッィクに追っかけているわけでもありません。人工性と自然との力関係を観察し、カメラを道具にして写真で記録するのです。年に三回か四回、一回の撮影に一週間ほどかけて福島宮城岩手の太平洋沿岸部を車で上下します。被災地の記録を目的にしているわけではないと言いましたが、結果的に記録していることにちがいありません。復興のプロセスについては強い疑問に思うこともあるし、怒りさえ感じることも多いですが、良いものも悪いものも、美しいものも醜いものもすべて等しく、記録を続けていきます。
-------昨年は、ヴェネチア・ピエンナーレ国際建築展の日本館でのプロジェクトにも携わっておられました。
山岸:ヴェネチアの展示は、日本館チームの一員として、歴史家や建築家や映画作家たちと協働させていただきました。日本館チームのテーマは「1970年代の建築をどう考えるか」ということでした。あらゆるジャンルでクリティカル・ポイントだった日本の70年代に、安藤忠雄さんや原広司さん、石山修武さんなど、いまや大御所の建築家がその壮年期に、どのように時代と対峙したのか。それをもっともよく表す建築作品を撮りおろすというのが僕の仕事でした。ごくふつうの住宅もあればセルフビルドの家、別荘、高層ビル、さまざまなタイプの建築作品を撮りました。当時の作品はいい意味で「やりたい放題」という感じで、たとえば象設計集団が手がけた、埼玉県の宮代町にあるコミュニティーセンター「進修館」は、思わず「なんじゃこりゃ?」って思ってしまうような建物なんです。最初から廃墟みたいな感じの建物で、柱なんかも大地から建ちあがるっていうよりは空から降ってきたみたいな感じで斜めに突き刺さっていて、それがコミュニティーセンターなんです。もちろん褒めてます(笑)。「建築」っていうよりは、もっと広い意味での「場所」になっている感じで、いまはコスプレイヤーの聖地にもなっているし、その横で地元のおじいちゃん、おばあちゃんたちが静かにコーヒーをすすっていて、外では子どもたちがヤカマシイ。老若男女いろんな人が集まって思い思いに使っていて、やはりそれを受けとめる場所がこの建築にちゃんとある、いや、使う人がそれをつくりだす感じかな。どっちが先だか分からない。しかし建築家がやるべきことをやって、あとから社会がついてくるというのか、建築作品の事後的な効果として社会的なものが生まれている感じがします。今とは順番が逆ですね。いまは社会的なものがすでに出来上がった前提として扱われている雰囲気が濃厚です。1970年代のやんちゃな建築に、僕は強いシンパシーを感じます。
-------「写真」や「建築」に興味を持たれてから、「建築写真」を撮るようになったきっかけはなんでしょう。子どもの頃から写真が好きでしたか?
山岸:この質問に対しては申し訳ないんですが、美談はありません(笑)。小さい頃から何かものをつくるのが好きだったということもないし、大学も経済学部ですし、機材としてのカメラなんて今も昔もぜんぜん興味がないんです。まあ本はよく読みました。あと旅行はたくさんしたな。アラスカ北極圏のインディアンの村に二ヶ月くらい滞在してカリブーとかムースを狩りに行ったりもしました。二十歳でした。若いね。まあいろいろなもの見たり聴いたりしているうちに最終的にたどり着いたみたいな感じです。人生なにが起きるか分かりません、いやホント。
写真をはじめたのも24歳ぐらいで、そのころ猛威をふるっていた(笑)いわゆる「私写真」的なものには馴染めなくて、ひたすら東京を歩きまわって町の無人の風景を撮っていました。いまも人間なんて撮りませんよ(笑)。町というか都市には当たり前ですが建築があって、だからごく自然にその延長で建築を意識するようになりました。
建築写真に惹かれたもうひとつの理由は、建築写真の形式性ですね。建築写真ってなんか堅苦しいでしょう?画面のなかで水平と垂直をきちんと出すとか、建物の奥行き感を表現するための光の当たり方にルールがあるとか、いろいろ約束事が多いからなんです。写真って誰でも撮れて何でもアリ、何でもオッケーですから、こんなふうにつくり手を律してくれる写真って建築写真しかありません。でもそういうものに律せられることではじめて、真に自由にものを作ることができるのだとぼくは思っています。この形式性は建築や絵画の伝統から由来していて、いわば古典性です。そういう、ものごとの古典性にアクセスできるっていうのは本当にかけがえのないことです。私は幸せ者です、いやホント。
-------今後のビジョンについて教えてください。
山岸:東北の写真は何百年何千年の先に残す記録というつもりでやっています。すぐに役立てようという気持ちはむしろありません。津波はまた何十年後かに必ず来ます。撮影はひたすら続けるのみです。撮影を続けながら、展覧会をして皆さんに見ていただきつつ、ゆくゆくは本にまとめたいですね。さきほども申しましたが、ぼくにとっては東北の写真も建築の写真も等価です。だからいつかは「東北」というフレームも外して、東北の写真も建築の写真も庭の写真もすべて一貫した同じ写真として見ていただきたいと思っています。そういう一貫した「ものの見方」をこそ、丁寧に提示していきたいと思っています。今日はありがとうございました。
 |
庭の写真1 京都迎賓館 |
 |
庭の写真2 蓮華院誕生寺 |
 |
「森山邸」の写真1 2010年4月6日、森山邸、東京都大田区 |

|
「森山邸」の写真2 2010年4月6日、森山邸、東京都大田区 |

|
東北の写真1 2011年5月1日、岩手県宮古市田老青砂里 |

|
東北の写真2 2011年10月25日、北上川、宮城県石巻市中野 |

|
ヴェネチア・ビエンナーレの写真1 「進修館」設計:象設計集団 |

|
ヴェネチア・ビエンナーレの写真2 「開拓者の家」設計:石山修武 |
 山岸剛(やまぎし たけし) 写真家。1976年生まれ。 1998年早稲田大学政治経済学部卒業、2001年早稲田大学芸術学校空間映像科卒業、2004年からフリーの写真家となる。2010-11年日本建築学会会誌『建築雑誌』編集委員、2014年第14回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館チームに参加。主な展覧会に「Tohoku-Lost, Left, Found」(2014)など。 |

#3 コンテナの可能性
デザインの力で製品の価値を再利用前より高めることを、アップサイクルと言いますが、そのような考え方でコンテナを建物に使われていることを知り、取材に行きました。訪ねたのは大阪市中央区瓦屋町にある、株式会社muura(ムーラ)。コンテナを利用したオフィス+ギャラリーを見たく、代表の中川氏にお願いして、完成前の状態からお邪魔しました。
ここでコンテナと呼んでいるのは、主に海上コンテナのことであり、世界中の流通を確保する為、その構造・技術的基準など、統一されて作られています。つまり、モジュールが同じなので、並べる、積み重ねることがシンプルに出来て、組み合わせがしやすい。レゴブロックのような世界が楽しめます。
さて、muuraではそのコンテナをどのように使われているのかと説明しますと…元々ナッツ製造の工場だった建物を半分残し、そこに20フィートのコンテナの一部を差し込んでいます。(入れ子構造のようにつなげる)さらに20フィートのコンテナを90度に回転させて設置。上から見るとコの字型の状態です。中庭のようにウッドデッキがあり、ぐるりとコンテナに囲まれた姿は、私の想像以上のものでした。きれいに並べるだけが、コンテナの魅力ではなく、中川さんの柔軟な発想は、まさに社名のごとく「村」を感じる空間でした。インテリアである棚やテーブルも日本のものづくりのスペシャリスト達が手がけた素敵なものばかり。「ヒトとモノ」「ヒトとヒト」が繋がるコミュニティになる事は間違いないと思います。
輸入大国の日本では、往路は海外から中身の詰まったコンテナが輸送されてきますが、復路は中身が空っぽの状態で送り返すとか…しかも輸送コストは同じ。この現状を救済するかのごとく、始まったコンテナデザイン。この空間づくりが日本で流通され、より日本のスピリッツが加わると、輸出も夢ではないかもしれませんね。
 muuraのコンテナができるまで。コンテナの選別から、専門家によるカット、クレーンでの設置。  外装と内装。コンテナの鉄っぽさを程よく残しつつ、木材、金属を用いた 装い新たなインテリア空間。併設カフェ「杏」の焼き菓子もとってもおいしい。  余談になりますが、トラックの幌を利用したバッグで有名なFREITAG社のチューリッヒ旗艦店。 高くそびえ立つコンテナの塔。さすがはアップサイクルの元祖。 会社のデザイン哲学を象徴しているかのように感じます。 |
 |
橋本征子(はしもと せいこ) スペースデザインカレッジ広報。 おしゃべりだいすき。CO2の排出量で光合成のお手伝いをしている。 と、思っている。 |

雨のち星、やがて恋 ~マジック・イン・ムーンライト~
やぁ、私だ。『ミッドナイト・イン・パリ』で時間を幾重にも超えてみせたウディ・アレンが、今度は舞台を南仏に移し、時代を1928年に設定した。脚本の名手として知られる監督が、当時の流行をうまく取り入れて粋な物語に仕立てるのが『マジック・イン・ムーンライト』である。
『英国王のスピーチ』で名を馳せたコリン・ファース演じるマジシャン(というより、現代的な感覚で言えば、イリュージョニスト)スタンリーは、実在した奇術師を土台にしていて、イギリス人なのにステージ上では中国人になりすまして行うエキゾチックなショーで人気を博している。綿密な計算に基づいた、種も仕掛けもある見世物を生業とする傍ら、何につけても疑り深い彼が時折請け負うのが、霊媒師や占い師の嘘を暴くこと。ある日、彼は幼なじみから依頼を受ける。コート・ダジュールの大富豪が信じこんで入れあげている若い女占い師の真贋を見抜いてほしいというのだ。出向いてみれば、容姿端麗なその女性ソフィ(今をときめくエマ・ストーンが扮する)は、マジシャンという身分を隠していたスタンリーの素性を軽やかに透視してみせる。さらには、富豪宅の婦人の亡き夫をこの世に呼び戻す降霊術まで披露する活躍っぷり(こうしたコックリさんさながらの儀式も20年代には頻繁に行われていた模様)。果たして、合理主義者にして稀代のニヒリストたるスタンリーは、隙のないソフィを追い詰めることができるのか!
ざっとそんな話かと思いきや、あろうことかスタンリーがソフィにうっかり惚れてしまったからさぁ大変というロマンチックコメディーに発展させるところがアレンの洒落たところだ。
基本的に全編ロケーション撮影を行った今作の中盤。ふたりが急接近する印象的な場面で使われているのが、1879年に建設されたニース天文台。これはオペラ座やモナコのカジノの設計で知られるシャルル・ガルニエとエッフェル塔を設計したギュスターヴ・エッフェルによる共作で、ドーム部分が開閉式。当時世界最大を誇った望遠鏡を擁する名建築だ。雨宿りで避難したスタンリーとソフィは、身を寄せ合って寒さをしのぎつつ、雷雨が去った後には、丸屋根を開けて一緒に星空を眺める。恋愛までをも合理的に捉え、人生すら計算し尽くしてきたスタンリーが、幼い頃よく遊んだという場所で、無垢な自分と対峙する。しかも、傍らには星空以上にまばゆい魔法使いの美女。稀代の奇術師もこの状況で味わうマジックには抗えまい。
物語のその後は銀幕に譲るとして、この作品には、20世紀初頭から存在した建築物が他にも続々と登場する。それらがこの素敵な小品においてどう機能しているのか考えながらの鑑賞を、読者諸賢にお勧めするところだ。
 (c)2014 GRAVIER PRODUCTIONS, INC. |
|
『マジック・イン・ムーンライト』 原題:Magic in the Moonlight |
 |
野村雅夫(のむら まさお) ラジオDJ/翻訳家 ラジオやテレビでの音楽番組を担当する他、イタリアの文化的お宝紹介グループ「京都ドーナッツクラブ」代表を務め、小説や映画字幕の翻訳なども手がける。 FM802 (Ciao! MUSICA / Fri. 12:00-18:00) Inter FM (Happy Hour! / Mon., Tue. 17:00-19:00) YTV (音楽ノチカラ / Wed. Midnight) |
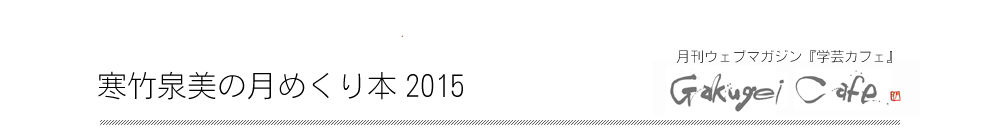
弥生本「日本酒ガールの関西ほろ酔い蔵さんぽ」 松浦すみれ (著)
お酒は弱い。でも大好きだ。1回の食事の席で2杯までしか飲めないから、何を飲むか、毎回真剣に考える。とりあえずビール!なんて、そんな気軽に決められない。2杯までならどんな種類でも大丈夫。ビールも飲むし、ワインも飲む。焼酎もカクテルも何でも飲む。でも、30代になってガツガツ量を食べるより、おいしいものを少量ずつつまむ方が好きになったら、日本酒の登場回数が多くなった。
日本酒は、銘柄ごとに味が全然違っていて面白いし、名前も風流。見たことがない銘柄があれば飲んでみたいし、人が飲んでいたらちょっと味見させてもらいたい。あれもおいしい、これもおいしい。で、結局どれが一番おいしいのかは分からない。何を飲んだのか名前も覚えられない。
だから蔵を見学するという発想もなかった。でもこの本を読んだら、日本酒がいとおしくなって、もっともっと好きになった。

日本酒ガールの関西ほろ酔い蔵さんぽ
松浦すみれ (著)
1400円 +税
出版社: コトコト (2015年2月)
この本を開くとまず、蔵見学のマナーについて書いてある。匂いのきつい香水は駄目、髪の毛が落ちないようにまとめて、滑りにくい靴を……と、いろいろ気をつけなきゃいけないんだな…と少し敷居の高さを少し感じながら次のページをめくると、「日本酒ができるまで」がイラスト付きで解説されていた。これを見たら、マナーとして書かれていたことのすべてに納得がいった。日本酒というのは本当に繊細なのだ。工業製品ではなく、料理や生きものに近い。米を蒸して発酵させてお酒を作る……それがどういうことなのか、よく分かった。
「作り手」について思いを馳せながら、著者と一緒に蔵めぐりをしていく。どんな場所にあって、どんな人たちが作っていて、どんな味わいのお酒なのかが、1つ1つあたたかいイラスト付きで紹介されている。著者の松浦すみれさんが元巫女さんだからなのか、文章もイラストも、あったかいだけじゃなく、すっと背筋が伸びるような品がある。たぶんこの本の底に流れているのは「感謝の視線」なのだと思う。太陽の恵みでお米を作り、そのお米からお酒を作り、そのお酒に出会って口に運ばれるまでのすべての過程にかかわる自然や人々への尊敬と愛情。
わたしが京都に住み始めてからもう13年経つけれど、そういえば観光地以外はあまりめぐったことはない。京都、滋賀、大阪、和歌山、奈良。それぞれの蔵の紹介を読んでいると関西という土地もいとおしくなった。足を延ばしたくなった。そして、ここに紹介されているお酒を飲んでみたい。蔵主さんと話してみたい。
お酒をきっかけに土地を愛し、人を愛すなんて、素敵なことだ。日本人のソウルフードであるお米と、その土地に密着したこの飲み物は、「日本酒」という名前が本当にふさわしい。
 |
寒竹泉美(かんちくいずみ) HP 小説家 京都在住。小説の面白さを本を読まない人にも広めたいというコンセプトのもと、さまざまな活動を展開している。 |


